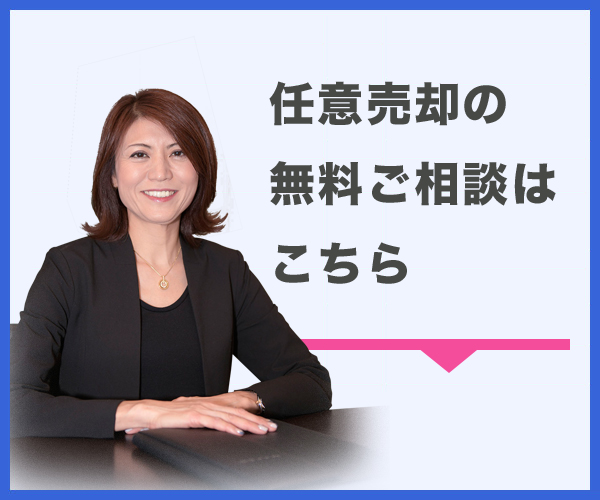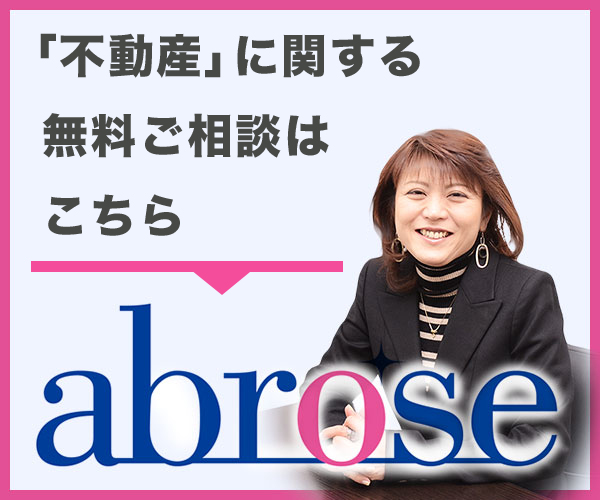2020.09.24
任意売却とハンコ代の意外な関係

住宅ローンを利用する際、住んでいる家に抵当権をかけた上でお金を借りてから、建築費などの支払いに充てるのが一般的です。しかし、それが複数の金融機関から負債がある場合、借りるお金は増えるのですが返済額が大きくなるリスクを高めてしまう事になります。今回は、任意売却とハンコ代の関係について紹介しましょう。
本来の役割とは
不動産の売却をする際に行うのが、登記簿謄本上における抵当権部分を削除する抵当権抹消からスタートします。つまり、債権者の許可がなければ成立しないのがルールです。その書類を法務局に提出した時点で抹消が成立します。
複数の債権者がいる場合には、優先権の上位である場合に対してのみ、配当が支払われない為に、下位になるお金がもらえない債権者達の同意を得る為の費用をハンコ代として扱っています。
二番抵当権者以降における債権回収額を少しでも回収する為に、同意に反対する事によって起こります。任意売却を行った場合、不動産売却後において債権者の方々に配分が行われ、協議をもって取り決めするようになっているほか配分についてのルールが設定されています。
競売をした場合、抵当権設定をした時間における順序が重要で、それが早い抵当権者が配分額を優先的に受け取れる可能性が高くなるので、競売のルールに関しては規定により設定されていることで、二番目の抵当権者に異議があってもそれに従う事になるわけです。
相場はいくらなのか?
基本的にいくら支払うかについては、この金額分必ず支払いなさいといった取り決めはありません。ですが、住宅金融支援機構ではトラブル防止の為、一定目安を掲示しておくルールを設けています。
少しでも問題を起こさないよう最低限の金額を目安に設定しており、抵当権者の方が複数存在する場合においては、一定金額をもらえるようになっていますので金額面において差が出てきますがもらえない可能性も大いにある為、やむなく了解に至るのです。
それでは、抵当権順位について説明しておきましょう。二番抵当権者の場合は30万円、三番抵当権者は20万円、四番抵当権者は10万円とそれぞれ設定されています。共通項目として、残元金における1割の設定で、指定された金額とのいずれかの低い額を選択するような基準になっています。複数の債権者が設定されている場合は目安の金額として考えましょう。
配分について
先に説明した一部は競売のケースでしたが、任意売却についてはここで改めて説明しましょう。配分に関しては各々で協議してから決定できる為、後順位抵当権者のうち一部は抵当権の抹消を協力するだけでも異論を唱えたがりますし、きちんとした取り決めをしてもらわないと話にならないといいたがる人もいるでしょう。
それをされたら債務者の方は痛手になるどころか、話にすらならなくなる為、任意売却が一切進められなくなる恐れがあります。ハンコ代における本質についてですが、債権者に対する配分を意味しますので任意売却のみ成立します。
競売になるとそれが一切発生しなくなる為、債権者に対する配分額となっています。しかしながら、それが発生する人とそうでない人の二種類が存在していますので、その件については次に説明しましょう。
成立条件
配分で一切もめずに話が順調に進んだ場合に関しては、そもそもハンコ代は一切発生せず物事を進めばよいだけの話です。もめない人に関する条件については、債権者が一人だけの時や複数存在しても合計額以上の金額で売却が可能である方となっているからです。
複数の債権者に関しては、裏ハンコ代と呼ばれる存在がある為、これが非常に厄介です。一番抵当権者が金融機関ならば、二番目以降は消費者金融などとなっているのがほとんどのケースです。
同意に拒否した場合の対応としては、買主に先に所有権を売却して「抵当権消滅請求」をする事で、後順位抵当権者が競売を行う権利を阻止する事が可能です。これは、「無剰余取消し」の規定により、競売を実施しても後順位抵当権者に無駄な行為となるので、消滅請求に応じる以外にないのです。
まとめ
ハンコ代と任意売却の関係について触れましたが、複数いる抵当権者に対して円滑に任意売却を進める意味でも重要な役割を果たしています。同意に拒否した場合の対応には、任意売却の経験と、あらゆる対抗措置に対応できる専門家に依頼する事が重要です。
任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。
本来の役割とは
不動産の売却をする際に行うのが、登記簿謄本上における抵当権部分を削除する抵当権抹消からスタートします。つまり、債権者の許可がなければ成立しないのがルールです。その書類を法務局に提出した時点で抹消が成立します。
複数の債権者がいる場合には、優先権の上位である場合に対してのみ、配当が支払われない為に、下位になるお金がもらえない債権者達の同意を得る為の費用をハンコ代として扱っています。
二番抵当権者以降における債権回収額を少しでも回収する為に、同意に反対する事によって起こります。任意売却を行った場合、不動産売却後において債権者の方々に配分が行われ、協議をもって取り決めするようになっているほか配分についてのルールが設定されています。
競売をした場合、抵当権設定をした時間における順序が重要で、それが早い抵当権者が配分額を優先的に受け取れる可能性が高くなるので、競売のルールに関しては規定により設定されていることで、二番目の抵当権者に異議があってもそれに従う事になるわけです。
相場はいくらなのか?
基本的にいくら支払うかについては、この金額分必ず支払いなさいといった取り決めはありません。ですが、住宅金融支援機構ではトラブル防止の為、一定目安を掲示しておくルールを設けています。
少しでも問題を起こさないよう最低限の金額を目安に設定しており、抵当権者の方が複数存在する場合においては、一定金額をもらえるようになっていますので金額面において差が出てきますがもらえない可能性も大いにある為、やむなく了解に至るのです。
それでは、抵当権順位について説明しておきましょう。二番抵当権者の場合は30万円、三番抵当権者は20万円、四番抵当権者は10万円とそれぞれ設定されています。共通項目として、残元金における1割の設定で、指定された金額とのいずれかの低い額を選択するような基準になっています。複数の債権者が設定されている場合は目安の金額として考えましょう。
配分について
先に説明した一部は競売のケースでしたが、任意売却についてはここで改めて説明しましょう。配分に関しては各々で協議してから決定できる為、後順位抵当権者のうち一部は抵当権の抹消を協力するだけでも異論を唱えたがりますし、きちんとした取り決めをしてもらわないと話にならないといいたがる人もいるでしょう。
それをされたら債務者の方は痛手になるどころか、話にすらならなくなる為、任意売却が一切進められなくなる恐れがあります。ハンコ代における本質についてですが、債権者に対する配分を意味しますので任意売却のみ成立します。
競売になるとそれが一切発生しなくなる為、債権者に対する配分額となっています。しかしながら、それが発生する人とそうでない人の二種類が存在していますので、その件については次に説明しましょう。
成立条件
配分で一切もめずに話が順調に進んだ場合に関しては、そもそもハンコ代は一切発生せず物事を進めばよいだけの話です。もめない人に関する条件については、債権者が一人だけの時や複数存在しても合計額以上の金額で売却が可能である方となっているからです。
複数の債権者に関しては、裏ハンコ代と呼ばれる存在がある為、これが非常に厄介です。一番抵当権者が金融機関ならば、二番目以降は消費者金融などとなっているのがほとんどのケースです。
同意に拒否した場合の対応としては、買主に先に所有権を売却して「抵当権消滅請求」をする事で、後順位抵当権者が競売を行う権利を阻止する事が可能です。これは、「無剰余取消し」の規定により、競売を実施しても後順位抵当権者に無駄な行為となるので、消滅請求に応じる以外にないのです。
まとめ
ハンコ代と任意売却の関係について触れましたが、複数いる抵当権者に対して円滑に任意売却を進める意味でも重要な役割を果たしています。同意に拒否した場合の対応には、任意売却の経験と、あらゆる対抗措置に対応できる専門家に依頼する事が重要です。
任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。